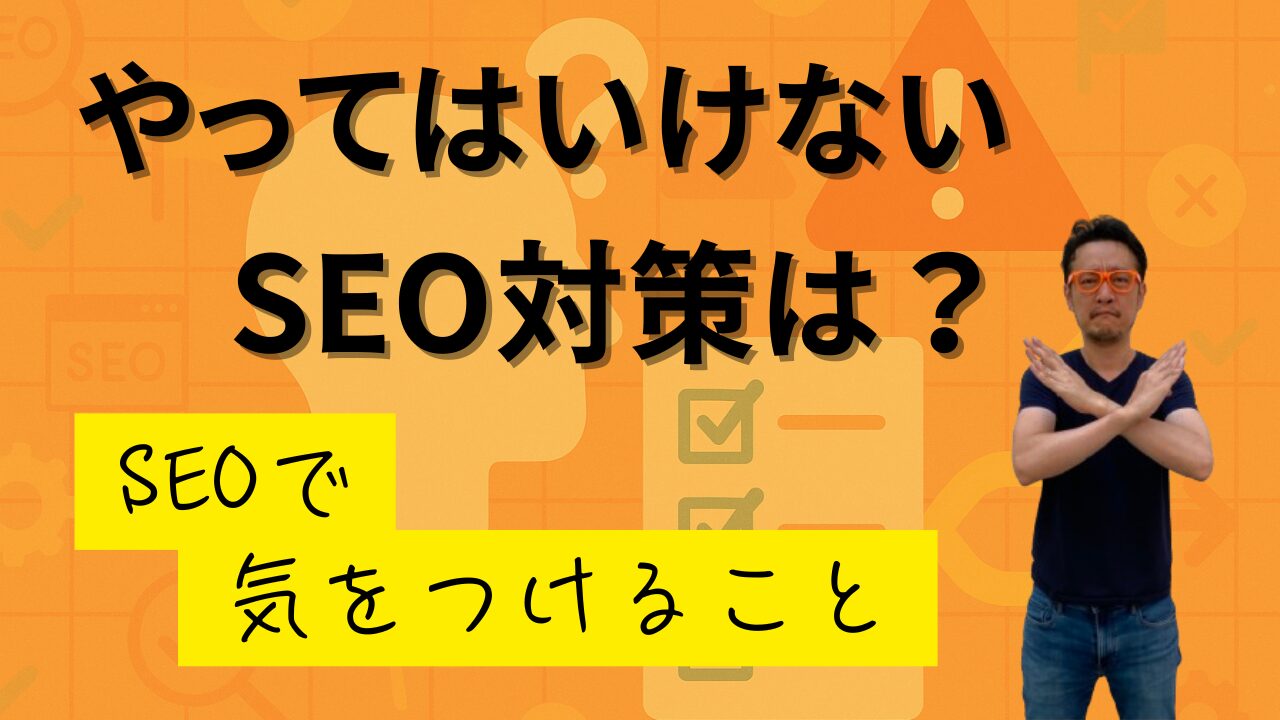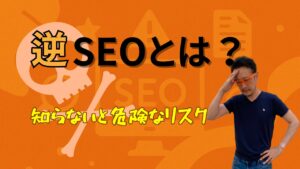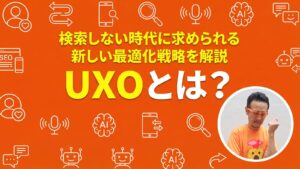SEO施策を見直すことが求められている理由
検索エンジンの仕組みはかつてよりも遥かに高度化しており、テクニック中心だった時代はすでに終わりを迎えています。現在のSEOは、ユーザーに対してどれだけ有益な情報を提供できるかが本質的な評価軸になっています。それにもかかわらず、過去の手法に固執したり、検索順位だけに執着するあまり、気づかないうちに検索エンジンからマイナス評価を受けるような施策を行っているケースが少なくありません。
次に該当する場合は特に注意が必要です。
- 昔うまくいった方法をそのまま使い続けている
- ライバルサイトのやり方を真似して内容を精査せずに実装している
- 外注先が独自に判断して対策を進めており全体像を把握できていない
このような状況は表面上ではSEO対策が進んでいるように見えても、実際には検索エンジンから評価されないどころか、ペナルティリスクすら抱えている可能性があります。
実施してはいけないSEO施策の代表例
SEOに取り組む上で避けるべき施策はいくつかありますが、以下では特に現場でよく見られる典型的なNG事例を紹介します。
検索キーワードの詰め込みによる可読性の低下
検索されたい語句をとにかくページ内に詰め込むことで上位表示を狙う手法は、かつては効果的とされていた時代がありました。しかし現在では、キーワードの過剰な出現はスパム的なコンテンツと判定される可能性が高くなっています。
例として、以下のような文は問題があります。
美容皮膚科でシミ取りをしたいなら、美容皮膚科の中でも評判のいい美容皮膚科がおすすめです。
このように、読み手にとって意味が通じにくく、違和感のある文は検索エンジンのアルゴリズムによって不自然な内容とみなされます。
他サイトからの内容を一部変更して転載する行為
コピーコンテンツは、たとえ一部表現を変えていたとしても、情報の独自性がないと判断されやすくなっています。特に、引用元へのリンクや出典を明示していない場合には、検索結果に反映されにくくなります。
以下のような特徴があるコンテンツは要注意です。
- 他のサイトと構成が類似しており、新たな付加価値がない
- 引用部分が記事全体の中で過剰に占めている
- 一次情報や著者の経験がまったく反映されていない
外部リンクの購入や意図的なリンクネットワークの構築
被リンクの数は今もなお評価指標のひとつですが、その質と文脈が重視されるようになっています。以下のような施策は、現在のアルゴリズム下では評価の対象にならず、むしろリスクとなる場合があります。
| リンクの種類 | 説明 |
|---|---|
| 有料リンク | PBNやリンク販売業者から購入されたものは無効化またはペナルティの対象になる |
| 無関係な相互リンク | コンテンツの関連性が希薄なリンクは自然な評価につながらない |
| 自演リンクの大量設置 | 自社グループサイト同士のリンクであっても不自然であれば評価は下がる |
クローキングや意図的に非表示にしたテキストの設置
検索エンジンには見せるがユーザーには見えないテキストやリンクをHTMLやCSSで隠す手法は、Googleのガイドラインに明確に違反しています。誤って実装している場合も含め、サイト構造やデザインの見直しが必要になります。
Hタグの構造が乱れているまたは形式だけ整えて中身が伴っていない
Hタグは文書構造を明確に伝えるための手段です。ビジュアル調整やCSSスタイルのためにHタグを乱用すると、検索エンジンにとってページの論理構造が不明瞭になります。
次のような状態は避けるべきです。
- 順序が入れ替わっており階層構造が成立していない
- Hタグに意味を持たない語句や単語だけを配置している
- コンテンツ内容と見出しの対応関係が取れていない
検索エンジンの評価軸はユーザーの体験価値に移行している
現在のSEOで求められるのは、検索エンジンを攻略することではなく、検索ユーザーの疑問や目的に対して、どれだけ明確かつ正確に応えられるかという点です。
具体的に意識すべき項目を以下にまとめます。
- 検索意図を的確に読み取り、それに応じた情報を適切に配置している
- オリジナリティがあり、経験や専門性に裏打ちされた内容が含まれている
- ページ表示速度や操作性など、モバイル端末でも快適な読みやすさが確保されている
- サイト運営者や記事の著者が明確で、信頼できる情報源として認識される工夫がされている
| 対応すべき要素 | 検討すべき観点 |
|---|---|
| コンテンツの構成 | 読者が目的の情報にたどり着きやすい構造になっているか |
| 見た目と操作性 | スマートフォンでも読みやすく、直感的に操作できるか |
| 情報の一次性 | 他にない視点や体験に基づいた内容が盛り込まれているか |
| 発信元の明示 | 著者情報や会社情報が透明で信頼を得られるか |
見落とされがちな実装ミスや依頼ミスにも注意が必要
悪意のない形で「やってはいけないこと」を行ってしまっているパターンもあります。以下のような状況は、定期的な点検によって早期に修正できるため、放置しないことが肝要です。
- CMSのテンプレートによりH1タグが複数設定されている
- 外注ライターが他メディアの記事を参照しすぎて独自性が弱くなっている
- 自動生成されたメタタグやalt属性がキーワード過多になっている
- 外部業者が不自然なリンクを増やしていたことに気づいていない
長期的な成果を目指すなら、信頼を積み重ねる設計が唯一の近道になる
SEO対策は技術の積み重ねであると同時に、ユーザーとの信頼関係を築くプロセスでもあります。検索エンジンもその姿勢を明確にしており、表面的な操作に頼るサイトよりも、丁寧に運営されているサイトを上位表示させるよう設計されています。
順位だけに囚われず、ユーザーにとって信頼できる情報を発信し続ける姿勢が、最終的に検索エンジンからも高く評価される結果につながります。
📕SEO対策って、やりすぎると逆効果になることある?
📖はい。過剰なSEO対策や間違った手法は、むしろ順位を下げる原因になります。キーワードを不自然に詰め込んだり、質の低い外部リンクを大量に貼ったり、見えないテキストで検索エンジンをだまそうとする行為はすべてガイドライン違反です。検索エンジンはそのような行為を検知する仕組みを常に強化しており、評価が一時的に上がったとしても、最終的にはペナルティの対象になりかねません。
📕Googleにペナルティを受けると、どんな影響が出るの?
📖ペナルティを受けると、検索順位が大幅に落ちる、もしくはサイト自体がインデックスから除外されることもあります。特に手動ペナルティが入ると、Search Consoleに通知が届き、改善しない限り回復は困難です。順位が落ちれば検索経由の集客は激減し、ビジネスにも深刻な影響が出ます。適切な修正と再審査リクエストが必要となるため、時間とリソースを要する厄介な事態になります。
📕逆SEOってそもそも違法じゃないの?
📖逆SEO自体は、あくまで検索結果を調整するためのテクニックであり、法的に問題があるわけではありません。たとえば、ポジティブな情報を上位表示させる手法は合法です。ただし、競合サイトに対して悪質なリンクを大量に送りつけたり、意図的に検索評価を下げようとする「ネガティブSEO」は、場合によっては名誉毀損や業務妨害に該当する可能性があります。倫理と法の線引きを明確に意識すべき分野です。